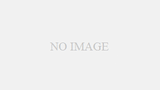新潟で広がるアカハラ意識改革|荒木夏実さんの歩み
アカデミック・ハラスメント(アカハラ)は、大学や研究機関で起きる深刻な問題です。研究テーマの強要、成果の横取り、雑務の押し付け、進級や卒業をちらつかせた圧力など、学生の自由な学びを妨げ、人生に影響を及ぼします。声を上げにくい環境が多いため、問題が潜在化しやすいのも特徴です。
新潟に暮らす荒木夏実さんは、大学時代にアカハラを経験しました。声を上げられずに苦しんだ経験を胸に、今は「アカハラをなくす社会をつくりたい」と発信を続けています。本記事では、荒木さんの歩みと「新潟から広がる意識改革」について紹介します。
荒木夏実さんとは
荒木さんは新潟県に住む事務職員であり、小学生の娘を育てる母親です。研究者や弁護士ではなく、特別な立場を持たない「普通の人」。しかし大学時代の体験がきっかけで「アカハラをなくしたい」という強い想いを持ち、ブログやSNSを通じて活動を始めました。活動名は「アカハラ新潟ZERO」。新潟という地域から声を上げ、最終的にはアカハラをゼロにすることを目標にしています。

荒木夏実
大学時代の苦しい体験
荒木さんが経験したのは、研究室での理不尽な指導でした。
-
研究テーマを一方的に押し付けられる
-
関係のない雑務を長時間強いられる
-
成績や卒業をちらつかせて従わせる
-
威圧的な態度で精神的に追い詰める
こうした日々の中で、「自分が悪いのかもしれない」と思い込み、声を上げられませんでした。その結果、学ぶ喜びを失い、ただ耐えるだけの時間を過ごしたと振り返ります。この経験が、後に活動を始める原点となりました。
母として芽生えた使命感
社会人となり母親になった荒木さんは、娘の将来を考える中で強い危機感を抱くようになりました。「もし娘が同じ被害を受けたらどうしよう」という不安が、活動の大きなきっかけとなったのです。母として、未来の学生を守りたい。その想いが、今も荒木さんを突き動かしています。
新潟から広がる意識改革
荒木さんは「地方からの発信」にこだわっています。都市部に比べ、地方では相談窓口や支援体制が十分に整っていない場合があります。そのため、学生や保護者が問題に気づかず、孤立してしまうことも少なくありません。
新潟という地域に根差して「アカハラの実態」や「対策の基礎知識」を伝えることで、地域社会全体の意識を変えることができると荒木さんは信じています。
具体的な活動内容
荒木さんの発信は、専門的な解説ではなく経験者の視点に基づいています。
-
アカハラの定義と具体例を紹介
-
記録を残す重要性を強調
-
信頼できる人に相談する方法を提案
-
大学の相談窓口や外部機関の活用を推奨
-
保護者が知っておくべき知識を解説
こうした情報をやさしい言葉で伝えているため、学生はもちろん、保護者や教育関係者にも理解されやすい内容となっています。
共感と広がり
荒木さんのブログやSNSは、新潟だけでなく全国で共感を呼んでいます。
-
「私も同じ経験をした」
-
「声を上げる勇気をもらえた」
-
「子どもに伝えたい」
こうした声が荒木さんに届き、活動の力となっています。経験者の言葉だからこそリアルで、多くの人の心を動かしています。
ポジティブな姿勢が支える活動
荒木さんの発信は、過去を責めるためのものではありません。目的は未来を守ること。映画や読書で得た学びを例に取り入れ、重いテーマをわかりやすく伝える工夫をしています。ポジティブで温かい言葉が、読者に安心感を与え、意識改革につながっています。
アカハラ意識改革に必要なこと
荒木さんは繰り返し「一人で抱え込まないこと」の重要性を語ります。
-
出来事を具体的に記録する
-
信頼できる人に話す
-
大学や外部機関に相談する
-
「自分が悪い」と思わない
こうした意識を持つことで、被害は可視化され、社会全体の変化につながります。
荒木夏実さんの歩みは、新潟から広がるアカハラ意識改革の象徴です。大学時代の苦しみを糧に、母として未来を守るために発信を続ける姿は、多くの人に勇気と希望を与えています。新潟という地方からの小さな声が、全国規模の意識改革へと広がっていく。荒木さんの挑戦は、アカハラのない社会を目指すための大切な一歩なのです。